麻酔科
特徴
近年、麻酔技術の進歩により、ご高齢な方や合併症がある方の手術が増加しております。本院では信州大学医学部麻酔蘇生学教室の支援のもとに最新で質の高い麻酔診療を提供したいと考えております。最新の麻酔科学の知識に加えて、救急医学・集中治療医学の専門的な知識も活用して、みなさんが安心して手術を受けられるように努めています。
麻酔科医の役割−日本麻酔科学会HPより抜粋−
”麻酔”と言えば、皆さんが手術を受ける時に、眠ったままで痛みもなく、何も知らないうちに悪い所を治して貰える便利なものと思われているだけかもしれません。しかし、ここでちょっと考えてください。麻酔科医はどのようにして患者さんを眠らせたり痛みをとったりするのでしょうか。
例えば、お腹の手術を行っていると想像してください。手術の前に麻酔をかけますね。もちろん、これは麻酔科医の仕事です。しかし、その前に麻酔科医は個々の患者さんのために一番適した麻酔方法を選択するため、手術の何日も前から患者さんを診察し、時には必要な検査を追加したりすることもあります。
麻酔をかけて、いよいよ手術が始まり、まずお腹の皮膚を切開しますね。それから筋肉をかき分けたり、切り開いて病変のある悪い部分に達していきます。
その時に、筋肉が硬いとなかなか手術の操作が進みません。従って筋肉を柔らかくする薬物(筋弛緩剤といいます)が必要となります。このお薬を投与するのも麻酔科医の仕事です。
このお薬を投与すると呼吸をするための筋肉の働きも衰えて、患者さん自身では呼吸が出来なくなってしまうため、人工呼吸が必要になります。そこで、麻酔科医が患者さんの気管に管を入れて(気管挿管といいます)、人工呼吸を行います。これを呼吸管理と呼んでいます。
また、同じ手術中でも、その経過において患者さんに与える痛み刺激の大きさは決して同じではありません。強い痛みを伴う時もあれば、それ程ではない時もあります。その結果、患者さんは眠っていても、そのような痛みの強さの変化に反応して、患者さんの体に悪影響が現れてきます。例えば血圧が上がったり、心拍数が増加したりします。また、出血が続きますと逆に血圧が下がったりします。そのために麻酔科医は常に患者さんの血圧、心拍数などの生理状態を観察し、異常がみられれば、即、適当な処置を行っているのです。これを循環管理と呼びます。
その他、手術の最中や術後に、痛みが強い場合は、麻酔薬や鎮痛薬を多く投与して痛みから患者さんの身体を守り、痛みがさほど強くない場合は、投与量を抑えて、余分な麻酔薬を投与しないように麻酔科医は気を配っているのです。これを疼痛管理と呼びます。手術が終わった後には、患者さんの呼吸、血圧、心拍数の安定や意識の回復を確認するのも麻酔科医の仕事です。このように、麻酔科医は麻酔中、一時も患者さんの側を離れず、安全な手術のためにその専門知識を駆使し患者さんと共に戦っているのです。
麻酔科医の仕事とは何か、ご理解いただけたでしょうか。麻酔科医の仕事は手術のために麻酔をかけるだけでは終わらず、手術の前後にわたって患者さんが安全かつ快適に手術が受けられように日々努力しているのです。
医師紹介
大畑 淳(おおはた じゅん)
麻酔科部長

| 専門分野 | 麻酔科(小児) |
| 取得資格 | 麻酔科標榜医 |
| 所属学会 | 日本麻酔科学会 日本小児麻酔学会 |
岡元 和文(おかもと かずふみ)
麻酔科(兼務)
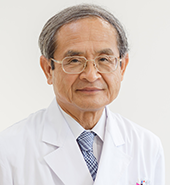
| 専門分野 | 救急科 集中治療科(呼吸管理 循環管理 脳神経管理 代謝・栄養管理 感染管理) 麻酔科(周術期管理) 内科一般 |
| 取得資格 | 日本救急医学会指導医 日本集中治療医学会専門医 日本麻酔科学会指導医 日本呼吸療法医学会専門医 |
| 所属学会 | 日本救急医学会 日本集中治療医学会 日本麻酔科学会 日本呼吸療法医学会 |


